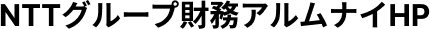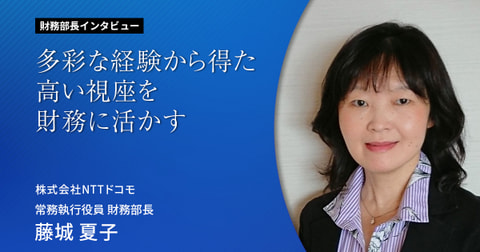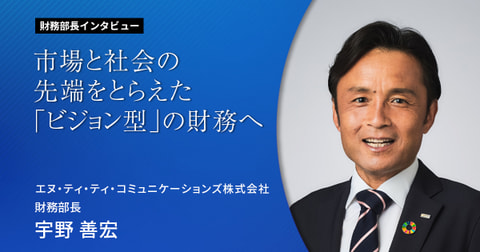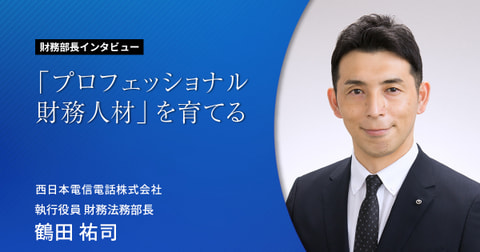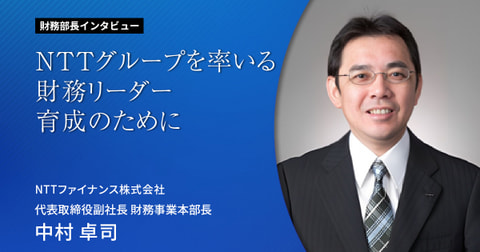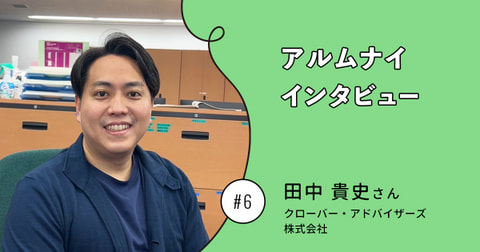「ファクト」から「真実」を導き出す力 財務部長インタビューVol.4 NTT株式会社 執行役員 財務部門長 中村 俊彦
SHARE

NTTグループ主要会社の財務部長が、これまでのキャリアと目指す未来について語る本連載。第4回はNTT株式会社の中村俊彦 財務部門長です。
持株会社であるNTT株式会社の財務リーダーとして、現在変革期を迎えているグループ全体の財務をけん引する立場にある中村部門長。リーダーとして大切にしているポリシーとは。そして、自身が考える、AI時代における価値ある財務人材の在り方とは。じっくりとお話を伺いました。
(プロフィール)
中村 俊彦(なかむら としひこ)
NTT株式会社 執行役員 財務部門長
東京大学法学部を卒業後、1992年日本電信電話株式会社に新卒入社。
持株会社やNTT東日本で主に財務会計に携わる。また、大蔵省(当時)証券局や、東京三菱銀行(現・三菱UFJ銀行)ニューヨーク拠点など、外部への出向を経験。
2020年NTT東日本の財務部長に着任し、2023年6月より現職。
――まずは、NTTに入社された頃のことを教えてください。
私が就職活動をしていた当時は、一度就職したら基本的には定年まで同じ会社で勤め上げるのが常識だった時代でした。自分の人生を捧げるにふさわしい仕事は何だろうと考え、人々の生活基盤を支えるインフラに携わりたいと思いました。
中でも、当時デジタル回線(ISDN)の導入を進めるなど、これから大きく発展を遂げて人々の生活を変えることになるであろう、インフラの最先端にあったNTTに入社を決めました。最新の技術に携わることで、自分自身も常に知識や常識をアップデートし、年齢を重ねてもリテラシーの高い人間であり続けたいという気持ちも、NTTを選んだ理由の一つです。
――入社してからのことを教えてください。
入社後は、横浜西支店で回線需要予測、通話料収入予測といった様々な営業支援業務を3年間経験しました。その中で「数字を扱う仕事も面白いかもしれない」と思い始め、その後の本配属の第三希望に「経理」と書いてみたところ、それが人事担当の目に止まったのか、半ば思いがけない形で財務キャリアの道を歩み始めることになりました。
財務としての最初の配属は、驚くべきことに、大蔵省(当時)証券局でした。初期配属先が外部への出向となるのは、極めて珍しいケースでした。証券局は証券取引所や証券会社の監督を行ったりルール作りを行ったりする部門で、現在は金融庁がこの機能を担っています。当時は国際的な金融犯罪が起き始めていたこともあり、各国が連携して取り締まりを行っていこうという機運が高まっていました。私が担っていたのは、こうした取り締まりを目的とした海外証券取引所との情報連携や、協力にあたっての窓口業務です。
――大蔵省で仕事をする中で、どんな発見がありましたか?
驚いたのは、官僚たちの仕事に対する視座の高さと目線の鋭さです。検証が甘い点、リスクとなり得る点を見抜き、補完して、100%の形に持って行く。この徹底ぶりには感服しました。
また、行政機関においては、決定事項やそれに至ったプロセスを全て文書化し、誰が見ても分かる形で残しておくという「文書主義」、いわゆる「見える化」が徹底されています。いつでも検証できる形にしておく、責任の所在を明確化することは、正しく効率的な行政運営に欠かせません。NTTも国営企業であった過去がありますので、この点は共通の価値観なのだろうと感じましたし、この文書主義が後の資金調達担当時代のプロジェクト(後述)において、非常に役に立つことになりました。
――大蔵省の後は、どのようなキャリアを歩まれたのですか?
大蔵省で2年間勤めた後の配属先は、当時のNTT本社経理部の資金担当でした。持株会社の発足をまたぎ、計6年間勤めました。主に資金調達担当として外国社債発行に携わっていたのですが、最も苦労したのが、持株会社への移行にあたっての業務でした。
社債を発行しているわけですから、会社が再編成されるにあたって、信用レベルが変わることがあってはなりません。そのため、再編後も信用を維持し続けるための設計と、格付け機関への説明が必要でした。
これを進めるにあたって、会社の信用力とはどこから来ているのか、その根本を改めて学びなおす必要に迫られました。ここで役立ったのが、前述した「見える化」です。幸いなことに、NTTにもあらゆる決定事項とそのプロセスが文書によって残されています。これらを読み込み、そのプロセスをさかのぼることで、「NTTという会社は、信用に関する重要事項を、何を根拠に、どう決定しているのか」という論理を理解することができました。
また、「最後は自分で決める」という姿勢を身に着けることができたのも、この時でした。私は社長が格付け機関からのインタビューに答える際の資料作りを担当していたのですが、それにあたり、外部コンサルタントの協力を仰いでいました。知見豊富な彼らからのアドバイスはもちろん参考になりましたが、資料の内容自体は、最終的には自分自身で決定しなくてはなりません。その根拠を自分自身の言葉で語ることができないと、チームはもちろん、相手(格付け機関)を納得させることができないからです。そのために、アドバイスは参考にしつつ、自分で調べて頭を動かし、判断し、自分の言葉で発信する。この訓練を積むことができたのは、大きな収穫でした。
――「後顧の憂いを遺さず」を、ご自身のポリシーとして掲げてくださっています。この意味について教えてください。
これは、中国の故事を由来とする言葉です。皇帝が出陣する際に、最も有能な家臣を国に残しておくことで、「自分が不在でも国のことを心配する必要がなかった」という意味合いで使われたのが最初だったと言われています。これが空間的な概念から時間的な概念へと転じて、将来(後輩)に苦労をかけないために、今自分ができることをしておこうという意味合いへと変化したようです。
このポリシーの形成に大きく関わったのが、2006年から2010年まで務めた、持株会社の会計担当課長・部長時代の経験です。グループ横断の会計ルール策定と、連結決算作成を主導する立場にあったのですが、この時、当社が監査を依頼していた主たる監査法人が解散してしまうという大きな出来事がありました。
そこで別の法人に新たに監査を依頼することになるわけですが、監査の視点やロジックは、監査法人によって異なります。そこで、過去の整理を見直さざるを得ない状況に立たされました。
とはいえ確かに、これまで慣例的に行ってきた整理の中でも、「本当にこのやり方で良いのだろうか」と疑問に感じていた事項があったのも事実です。そこで、「持続的な存在である企業としてのあるべき姿」へと近づく、言い換えれば「ガバナンスを強化するための良い機会」と捉え、腹を据えて向き合うことにしました。
――とはいえ、財務の数値への影響は避けられないのではないでしょうか。
もちろん、整理の見直しに伴う財務への影響は、最小限に抑えられるよう努力しました。しかし、今決断しなければ後々に悪影響を及ぼしかねない事項に関しては、短期的な数字の悪化というダメージを飲んででも決断しなければなりませんし、社内外に自分の言葉で説明する必要があります。ハードな任務ではありましたが、未来の後輩に禍根を残さずに済んだという意味では、やり切ることができて良かったと思っています。
――現在中村部門長は、持株会社の財務の責任者でいらっしゃいます。この役割の中で意識されていることについて教えてください。
一言で申し上げると、「攻めのバランス」です。私たち持株会社財務部門は現在、3つの役割を持っていると認識しています。一つめは「変革を牽引するリーダー」。現在大変革期を迎えているNTTグループを導くための役割です。二つめは「規律を守る番人」。前述したような未来への禍根を残さないために、ルールの運用を徹底する役割です。最後は「事業に伴走するサポーター」。当社グループが利益を得られているのは、実際にお客様にサービスを提供している事業部門の方々のおかげです。彼らに対し、上から目線でルールを説いていても、事業成長を導くことはできません。ルールに則った適切な事業成長を実現するための支援を行っていくことが、私たち財務には求められています。
これら3つの役割のバランスをとろうと考えたとき、ともすると保守的・消極的な姿勢になりがちです。そうではなく、リスクテイクしながら攻めの姿勢でバランスをとる。どの役割においても最大限の力を発揮するように努めると、自然にバランスがついてくる。これも、私が大切にしているポリシーです。
そしてもう一つ、既存のやり方・ルールを更新していく役割も今、私には求められているのだと思っています。分かりやすい例を挙げると、AI活用です。財務分野においては、計算や分析など、AIによって代替可能な業務が多くありますので、活用しない手はありません。しかし既存のやり方・ルールは、AIを前提としていないものがほとんどです。財務人材がコア業務に集中し、財務のオペレーションをアップデートしていく(世の中についていく)ためにも、これらのやり方・ルールの賞味期限を常に見直していくことが必要です。
私たち財務人材のこれからのコア業務は、一言で言い表すなら「ファクト」から「真実」を導き出すことになっていくでしょう。数字はファクトですから、変わることがありません。しかしその数字が意味することは、解釈によって様々な捉え方が可能となります。その中で、ファクトをどのように解釈し、どのように「真実」をつかむか。AIは解釈方法の提示はしてくれるでしょうが、その中からどれを選ぶかは、自分の頭で判断するしかないのです。そのための資質を養うことが、今後の財務人材には求められていると感じています。
――財務アルムナイコミュニティに期待されていることはありますか。
財務スキルは汎用性が高いので、人材流動性も高いです。一方で、時代の流れに取り残されないためには、前述したようなAI等の技術進化を先取りしていく自己研鑽が不可欠だと思います。そういった意味では、アルムナイの皆さん同士で、会社と個人の「今」についての情報交換ができることは、とても有意義だと感じています。
皆さんが在籍していた頃から比較すると、NTTグループ自体も大きく変化したと思います。そんな今の我々についてぜひお伝えしたいですし、皆さんの今についてもぜひ教えてください。互いにAI時代の価値ある財務人材として成長し続けられるよう、切磋琢磨し合える関係を築いていけたら嬉しいです。
- CATEGORY :財務部長インタビュー